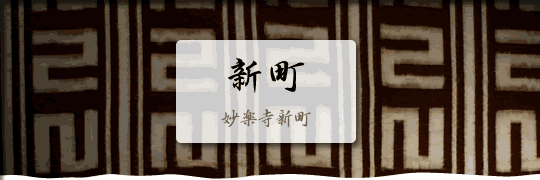|
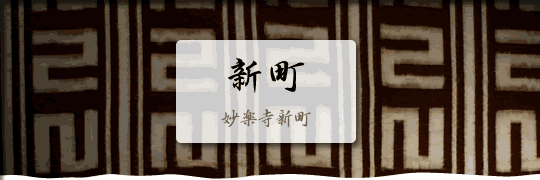
 現在の古門戸町3番地東側から同4番地西側にあった縦筋の町。江戸中期は妙楽寺町22軒、妙楽寺裏町9軒に対し、新町は18軒あったが、その後住民が減り事実上妙楽寺町に吸収されたかたちとなった。 現在の古門戸町3番地東側から同4番地西側にあった縦筋の町。江戸中期は妙楽寺町22軒、妙楽寺裏町9軒に対し、新町は18軒あったが、その後住民が減り事実上妙楽寺町に吸収されたかたちとなった。
昭和41年(1966年)2月の町界町名整理まで町は存在したが、大黒流の当番も昭和6年(1931年)を最後に単独で務めることはなくなった。
町名の由来である妙楽寺は正和5年(1316年)頃に建立された広大な寺であったという。天文7年(1538年)の火災で焼失し、現在は御供所町に移っている。
現存する当番法被がまだ見つかっておらず、福岡市博物館に所蔵されるものは写真を参考に博物館が独自に制作したものである。 |
|